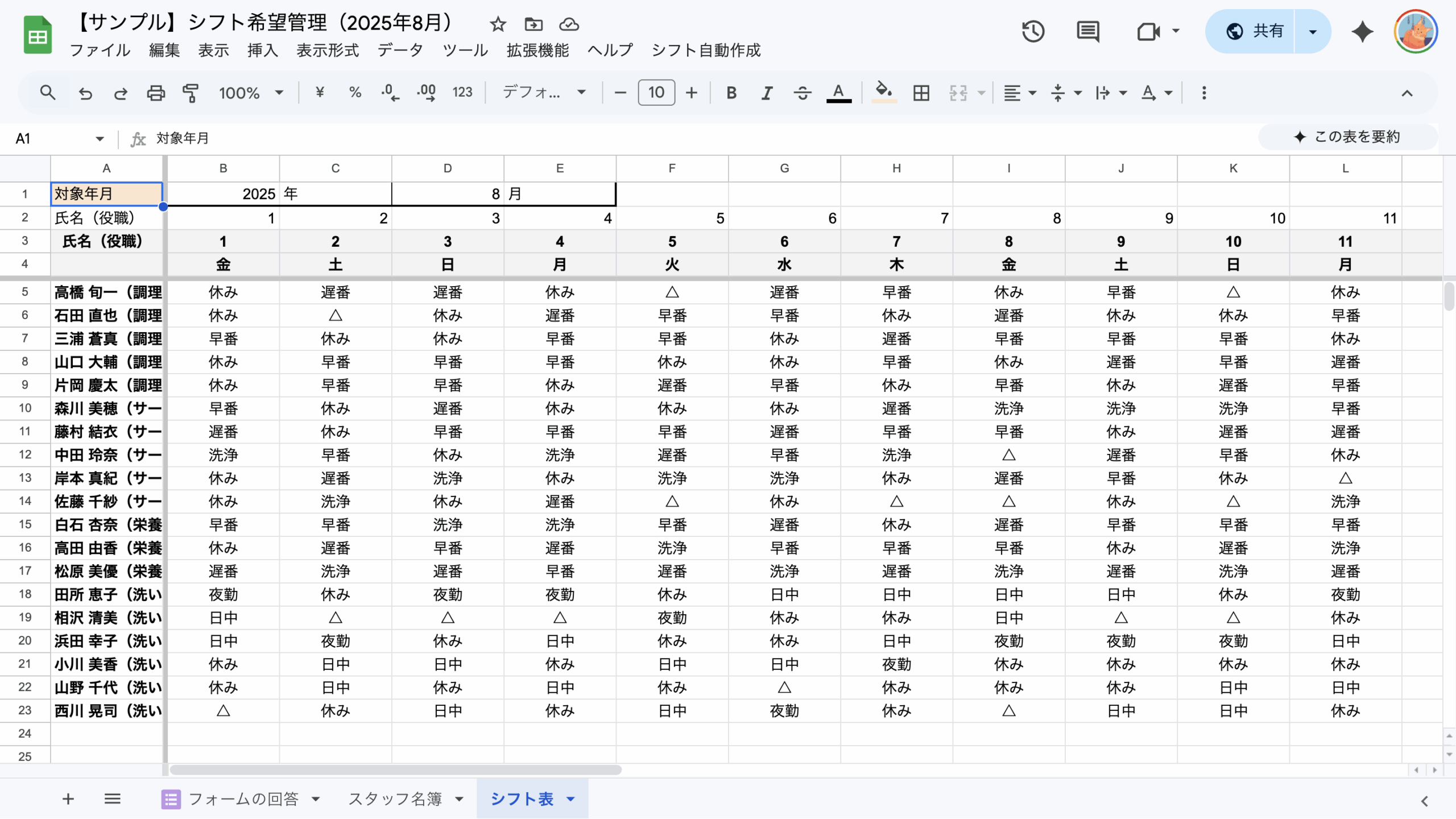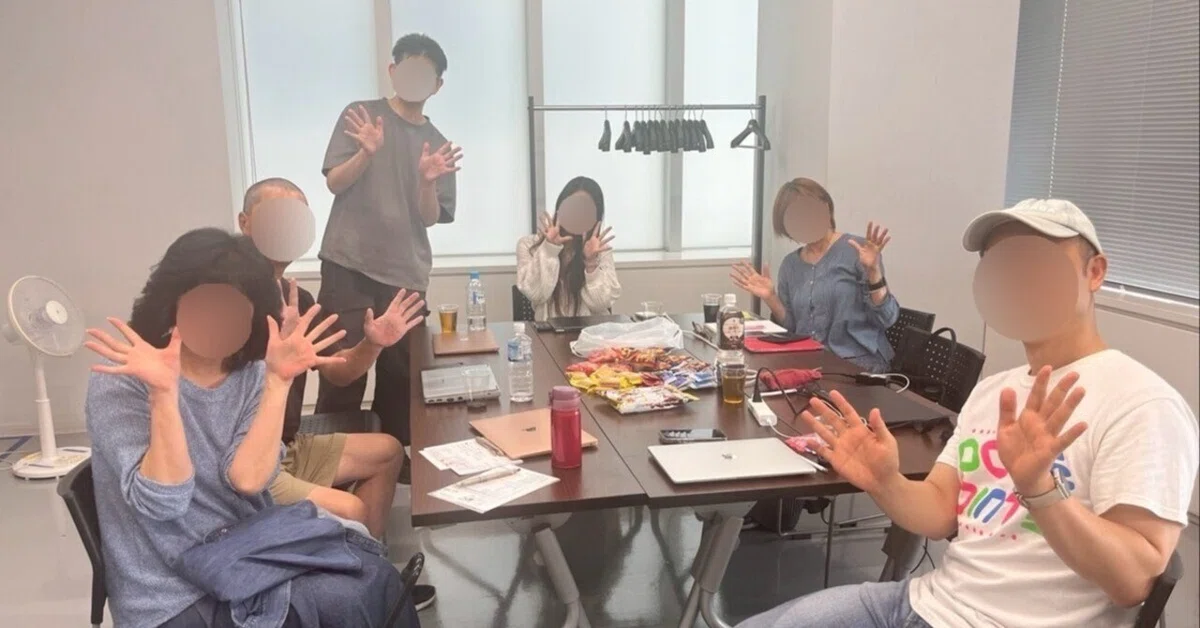
先日、大宮でAIカフェイベント「第1回AIカフェ」を開催しました!
教育や福祉、ビジネス、そして「自分をもっと知りたい」といった個人的な興味まで、本当に色々な分野で活躍されている方々にお集まりいただき、「AIって私たちの未来をどう変えるんだろう?」というテーマで、わきあいあいと、そして時には熱く語り合いました。
今回は、全5回にわたってお届けした開催レポートをぎゅっと一つにまとめて、当日の雰囲気やAIが持つ無限の可能性、そして私たちがAIと賢く付き合っていくためのヒントをお届けします。
AIは仕事や創作活動の「有能な相棒」!
最近、AIは単なる便利な道具というより、仕事や創作活動における優秀な「秘書」や「アシスタント」のような存在になってきましたよね。人間相手だと気を使ってしまったり、何度もやり取りが必要だったりしますが、AIならそんなコミュニケーションコストはゼロ。知りたいことや作ってほしいものを伝えれば、圧倒的なスピードで応えてくれます。
■ コンテンツ作りが驚くほどラクになる!AIとデザインツールの連携ワザ
セミナーのスライド、ウェブサイトのバナー、SNSの投稿、さらには研修で使う教材や認定証まで、AIはあらゆるコンテンツ作成の場面で大活躍しています。
例えばスライド作りなら、まずChatGPTのようなAIに「こんなセミナーをやりたいんだけど、構成案を考えて」と相談するところからスタート。過去の資料を読み込ませて「もっと良くするにはどうしたらいい?」とアドバイスをもらうこともでき、まるで優秀な壁打ち相手のように思考を整理してくれます。
テキストができあがったら、次はデザインです。GenSparkというツールを使えば、テキストを基に自動でおしゃれなスライドを生成してくれます。特に、作るのが面倒なフローチャートも一瞬で完成させてしまうのには、参加者さんからも「すごい!」と驚きの声が上がりました。最後の仕上げにCanvaで少し手直しを加えれば、もうプロ級のクオリティです。
SNS、特にInstagramのリール動画の作成では、Canvaの「キャンバシート」機能が「革命的!」と話題になりました。Excelのようなシートに投稿したい内容を書き込んでいくだけで、複数のリール動画を一括で自動生成してくれるんです。「これを使えば、10分で2週間分の投稿が作れちゃう」という活用例には、みんな本当にびっくりしていました。
この1年でCanva自体もすさまじい進化を遂げていて、画像編集だけでなく、動画、PDF教材、ホームページまで作れる**「超万能ツール」**になっています。デザインスキルに自信がない人でも、質の高いコンテンツを簡単に作れるのが嬉しいポイント。クラウド上で動くのでPCの容量を気にしなくていいし、自動保存でいつでもどこでも作業を再開できる手軽さも魅力です。
■ 毎日の記録や情報管理もAIにおまかせ
日々の記録や報告書の作成に多くの時間がかかる現場、例えば療育の現場などでは、AI(特にClaudeが活躍!)の活用が大きな助けになる、という話で盛り上がりました。
活動の様子を写真に撮ってAIに見せれば、文字起こしから内容の要約、そして「次はこんなアプローチはどうでしょう?」といった対策の提案までしてくれます。これなら、短時間で質の高い記録が作れますし、人手不足が深刻な現場でも、経験の浅い指導員さんがスムーズに事業所を運営していく助けになります。政府のガイドラインに沿った提出書類の作成もAIに任せれば、私たちはもっと子どもたちと向き合う本質的な時間に集中できるようになる、そんな未来が見えてきました。
AIが心に寄り添い、個性を育む未来
AIは、業務効率化だけでなく、教育や福祉の分野、特に療育の現場で、子どもたちの個性を伸ばし、心をサポートする新しい形を示してくれました。
■ 「グレーゾーン」の子どもたちが持つ、自分だけの輝きを見つける
社会の「普通」に合わせようとすることで、生きづらさを感じてしまう「グレーゾーン」の子どもたち。そんな子たちが持つ、その子だけのユニークな輝きを最大限に引き出し、一人でも自立して生きていけるようにサポートすることこそ「本当の療育」ではないか──そんな熱い思いが共有されました。
具体的なアイデアとして出たのが、筆跡診断にAIを活用したアプリです。書道や筆跡診断の専門家の方からは、「字の変化は、性格の変化にもつながる」というお話がありました。AIが筆跡からその子の強みや課題を分析し、人付き合いや明るさといった心の成長をサポートできるかもしれない、と。黙々と字を書く作業は、心の障害を持つ子が得意なこともあり、AIが「上手だね!」と褒めてくれることで、自信につながるのでは、という期待が寄せられました。
■ AIが、親と子の素敵な関係のきっかけに
療育の現場では、親御さんの期待とお子さんの能力とのギャップや、おじいちゃんおばあちゃん世代との考え方の違いといった課題もあります。そこでAIが、お子さんの得意なことや素敵な個性を「見える化」してあげることで、親御さんが「うちの子にはこんな素晴らしいところがあったんだ!」と気づくきっかけになるかもしれません。「普通に」という捉え方が変わり、子ども自身が自分の才能に気づく「きっかけ」をAIが与えてくれる。そんな、親と子の喜びを分かち合える素晴らしい未来が期待されています。
■ AIは、あなたの「個人的なサポート役」
AIは、個人の心のケアでも大きな役割を果たしそうです。ある参加者さんからは、AI(特にChatGPT)に悩みを相談したところ、絶対に否定せず、どんな話も「うんうん」と受け止めてくれたことが、とても心の支えになったという体験談が語られました。株で失敗した話でさえ、「でも、この経験でこんな学びがありましたよね」と良い面を見つけて褒めてくれたことに感動したそうです。
また、落ち込んでいる時に、励ましてほしい有名人(例えば孫悟空やエガちゃん!)になりきって返信してくれるAIに元気をもらった、というユニークなエピソードも。この1年で、AIが人の感情に寄り添う能力をぐんぐん学習している、と感じている方もいました。
AIは私たちの悩みを受け止め、自己理解を深めるためのパートナーにもなりうる。そんな大きな可能性を感じさせてくれました。
AI時代のキャリアと、賢いツールの選び方
目まぐるしく進化するAIは、私たちの働き方やキャリアにも大きな影響を与えています。AIに仕事が奪われるという不安がある一方で、AIを使いこなせば、一人でできることの幅がぐっと広がるという希望も見えてきました。
■ 働き方はどう変わる?AIとの共存を考える
かつては「稼ぎたいならエンジニア」と言われた時代もありましたが、今やMicrosoftのような大企業でさえ、AIの方がミスなく速く仕事ができるという理由でエンジニアを解雇している、という話が出ました。税理士や弁護士といった専門職の仕事も、AIで代替できるようになってきています。「国家資格を持つ専門家でさえこうなのだから…」と、私たちがこれまで「安定」だと信じてきたキャリアの定義が、根本から変わろうとしていることを実感させられました。
でも、これはただ怖いだけの話ではありません。AIは非常に優秀な「秘書」や「アシスタント」として、私たちの仕事の範囲を劇的に広げてくれます。人間相手のような気遣いや時間のロスなく、その場でサッと指示を修正できるのも強みです。AIがもたらす変化はもう避けられません。だからこそ、その変化をきちんと理解し、AIとどう一緒に働いていくかを考えていくことが大切だと感じます。
■ どのAIツールがいい?「個性」を理解して賢く使い分けるヒント
AIカフェでは、ChatGPT、Claude、Geminiといった主要なAIツールの「どれがいいの?」「どう使い分けてる?」という話題でも盛り上がりました。
結論から言うと、各ツールには明確な「個性」があるので、「何を作りたいか」「何のために使うか」で使い分けるのがベスト、ということです。
- Claude: 日本の法律のような「正解」が決まっている質問は少し苦手かも、という意見も。一方で、日本人の感情に寄り添うのが得意で、ユーザーを「褒める」のが上手。メンタルケアの相談相手や、女性的でやわらかい表現を求める時に向いているようです。
- ChatGPT: 「真面目」「左脳的」で、**「分析・分類が得意」**という声が多かったです。使えば使うほどユーザーの癖を学習して、回答を「自分好み」に調整してくれるのが特徴。フォルダ分け機能も便利です。画像生成も比較的得意。
- Gemini: 「感情表現が豊か」という点が印象的。Googleのサービスとの連携がスムーズで、ストレージが付いてくるなど、コストパフォーマンスの良さも評価されていました。音声データを活用するNote LM機能も便利です。
ちなみに画像生成については、Canvaに搭載されているAI機能はまだ発展途上で、思わず笑ってしまうような面白い(?)画像が出てくることも。高品質な画像を求めるなら、ChatGPTやMidjourney、Stable Diffusionなどを試してみるのが良さそうです。
どのツールに課金するかは悩ましい問題ですが、変化が速い業界なので、月額契約で柔軟に見直していくのが良いかもしれません。大切なのは、自分の目的や「表現したいこと」に合わせてツールを選ぶこと。
そして、AIは単に「答えをもらう」ためだけのものではありません。AIと対話することで、「自分は何に困っているのか、何をしたいのか」を明確にしていく、つまり**「問題を定義する」手助けにもなる**、という深い気づきも共有されました。
まとめ:AIと共に、もっとワクワクする未来へ
今回の「第1回AIカフェ」を通じて、AIが教育や福祉の現場から、日々の仕事、そして個人の心のサポートまで、本当に幅広い可能性を秘めていることを改めて実感しました。
これからの時代を楽しく生き抜く秘訣は、AIツールの「個性」を理解して、自分の目的に合わせて賢く「使い分ける」こと。
最新情報を追いかけるだけでなく、実際にツールを使っている人たちのリアルな声を聞き、具体的な使い方や「使ってみてどうだった?」を知る時間は、本当に多くの発見と学びに満ちていました。AIはもはや、単に作業を効率化するだけのものではなく、私たちの創造性を刺激し、**自己理解を深め、より豊かな人間関係を築くための「有能な相棒」**になりつつあります。
AIの可能性は無限大です。これからも、この変化を前向きに楽しんで、AIと一緒にもっとワクワクする未来を作っていけたら嬉しいです。